本書では、即断即決即実行のPDCAことにより圧倒的な成果をあげることが出来ると著者は言い切っています。サイクルを回すとうまくいく理由は、
・先手を打てる
・生産性が上がる
・周囲から信頼される
・部下もつられて素早く動く
・組織全体が活気づく
ということです。「では、どうすれば即断即決即実行できるようになるのか?」という問いが生まれると思いますが、それは、“全体観を持つこと”です。全体観を持てば、おっかなびっくりではなく、一定の確信のうえで判断できるようになる。表面的な業務の流れだけでなく人間関係を含めた全体を見ているので、部分最適の解にとらわれることなく、ベストな案を選択できる。失敗も少ない。当然、検証の手間も短縮され、成果を出すまでのスピードも大いに上がるというわけです。
次に考えるのが「では、どうすれば全体観を持つことができるか?」という問いでしょう。本書には4つの能力( 仮説構築力 、 情報収集力 、 観察力 、 洞察力 )が必要とされています。即断即決・即実行と全体観、4つの能力を図で表すと以下のようになります。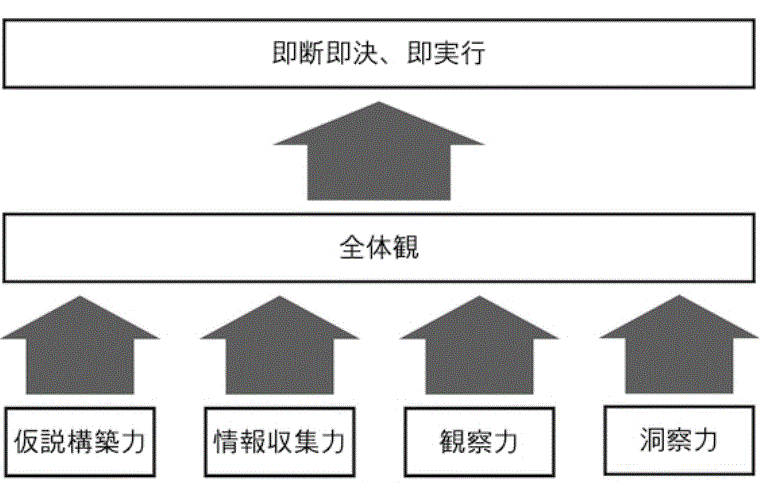
この4つの能力が支えとなって、最終的には即断即決・即実行の”すぐやる人”につながるというわけです。「では、4つの能力はどのように鍛えればいいのでしょう?」本書には、2つの方法(オプション、フレームワーク)が紹介されています。この2つを練習し、使いこなせるようになれば、迷いやためらい、躊躇、先延ばしをオサラバし、”すぐやる人”になれるということです。本書のポイントで、この2つの練習方法ついて解説していきます。
最後に、本書の前提として、赤羽さん前作のゼロ秒思考を理解していることが前提となります。メモ書きとオプションとフレームワークを組み合わせることで、より頭が整理され思考力が高められて、全体観が養われることになるので、メモ書きがベースになることは赤羽さんのすべての主張の根本という理解が必要だと思います。
| ●本書のPoint |
| オプションを活用して全体観を養う方法 人が正確で素早い意思決定をすることをイメージしてほしい。主要な選択肢を挙げ、すばやく評価するスキルがあれば、見落としなく複数の施策を評価し、最善の手を選ぶことができる。この選択肢をオプションと本書で定義している。「オプション」での思考が不十分だと、かなりの割合で最善を尽くせない。それどころか手痛いミスを犯してしまうことにもなる。ビジネスであれプライベートであれ、人間の行動は選択肢から選ぶという行為の連続だ。極論すれば、それがほぼ全てと言ってもよい。つまりオプションの精度を上げることが 正確で素早い意思決定 のポイントである。以下にオプションを使った意思決定の3つのステップ例を紹介するので、毎日のメモ書きなどでも取り入れて 正確で素早い意思決定レベルを向上させて行きましょう。まさにそれが全体観を高めることに繋がります。 1.選択肢を挙げる 年末の過ごし方で、まずはどんな選択肢があるか?を考えます。 ・自宅でのんびり過ごす ・実家に帰る ・旅行に行く(国内・海外) 2.評価項目を決める 次に各選択肢を評価する項目を決めます。例えば、 ・楽しさ ・親孝行の度合い ・予算(コストのやすさ) のような感じです。 評価項目は多ければいいというわけではないです。なので、主要なものを挙げたら、最後のステップに行きましょう。 3.評価する 1で挙げた選択肢を、2の評価項目で評価します。評価は、 ◎(4点) ○(2点) △(1点) ×(0点) の4段階です。こんな大雑把でいいのか?と疑問に思われるかもしれませんが、大丈夫です。 そして、◎○△×をつけ終わったら合計点を出します。最高得点のもの選べば、自然と全体最適な選択をすることができます。 以下のイメージです。 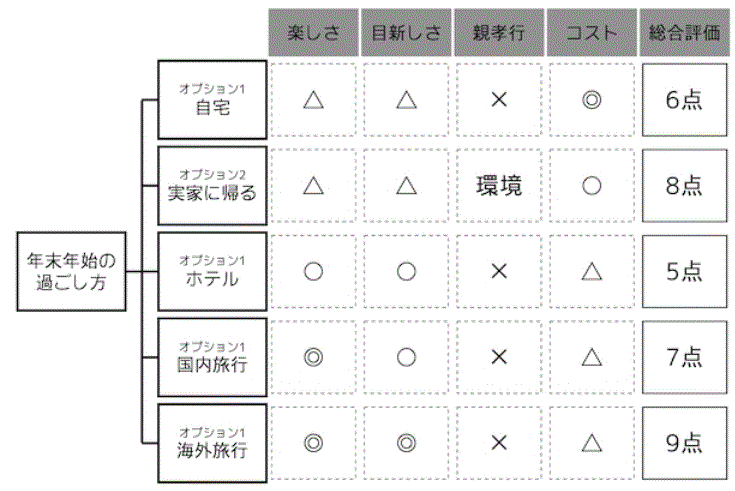 |
| フレームワークを活用して全体観を養う フレームワークで一番簡単で手軽なものは2×2の枠組です。そして、この2×2の枠組を使いこなせれば、相当な威力を発揮すると言います。 フレームワークを使えば、複雑な状況も整理して理解しやすくなりますし、ヌケモレもなくなります。自分ひとりでなく、複数人で議論しているときは認識を一致させるのにも役立ちます。そして、フレームワークを使う場合は、以下のチェック項目で確認すると、精度の高いものができます。ぜひ、活用してください。 ・いま何を整理しようとしているのか ・ その整理するものを、どういう軸で整理すると最も意味があるのか ・ 2×2に分けたとき、縦軸・横軸それぞれの2つの箱のラベルは適切か ・ 4つの箱それぞれに適切な内容を記入することができるか ・ タイトル、軸、ラベル、分類した内容の間で齟齬がないか ・ 全体として有用なのか 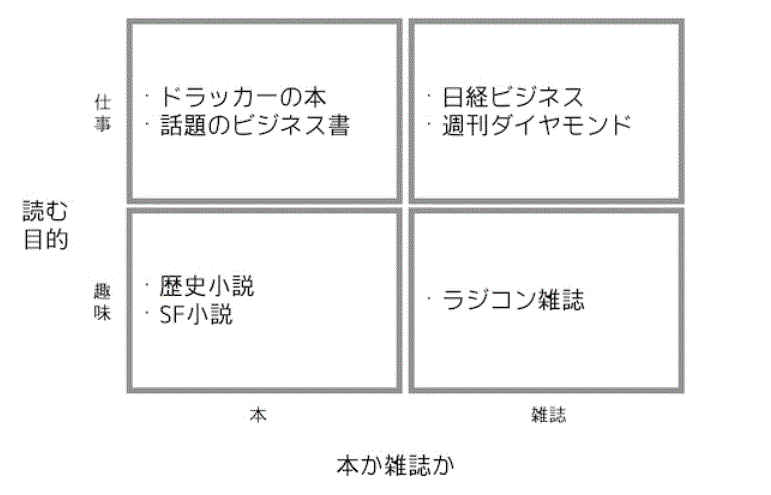 |
第1章 即断即決、即実行はなぜ難しいのか?
即断即決、即実行しないのは多くの場合「逃げ」である
●ためらい、迷い、躊躇、逡巡に価値はない
●本当に優れたリーダーは即断即決、即実行している
●即断即決、即実行は「猪突猛進」ではない
即断即決、即実行すべき6つの理由
●即断即決、即実行すると先手を打てる
●即断即決、即実行するとPDCAを早く何度も回せる
●即断即決、即実行すると生産性が上がる
●即断即決、即実行すると周囲から信頼される
●即断即決、即実行すると部下もつられて素早く動く
●即断即決、即実行すると組織全体が活気づく
即断即決、即実行を妨げる心理的ブロックと解決法
●情報を集めきらないと不安、怖い
●すぐ頭がいっぱいになる
●予定を変えることが不安。何もかも決めておきたい
●人に依頼すること、頼ることが面倒、不安
●選択肢を出し切らないと不安、怖い
●「失敗したらどうしよう」と、やる前に悩む
●即断即決、即実行に拒否感、アレルギーがある
●わかっていても動けない
第2章 即断即決、即実行を支えるもの
全体観がないから動けない
●「全体観」とは何か
●リーダーに不可欠な全体観
●全体観を持てる人が備えているもの
全体観を持つための2つのトレーニング
●「オプション」とは何か
●「フレームワーク」とは何か
●「オプション」「フレームワーク」と全体観
第3章 即断即決、即実行のツール① オプション
オプションのしくみとポイント
●大事な選択肢を漏らさず挙げ、評価する
選択肢を素早く適切に挙げるコツ
●まずは思い込みを排除し、最大限に考える
●本当の目的と制限に従って絞り込む
●全体観とともに、「親子・兄弟関係」に注意して見直す
オプションを評価する最適な方法
●4〜5個の評価基準を決める
●チームに関わる決定をする際の注意点
●オプションは「◎○△×」で評価する
●オプション評価の具体的なステップ
●簡易版の「メリット・デメリット」方式もある
オプションを使いこなすトレーニング
●オプションを習慣化する工夫
●オプション評価の例を蓄積する
●オプション習得のためのA4メモ書き
第4章 即断即決、即実行のツール② フレームワーク
フレームワークのしくみとポイント
●対象を漏れなくダブりなく分類する
正しいフレームワークの作り方、チェックの方法
①いま何を整理しようとしているのか
②整理するものを、どういう軸で分けると最も意味があるのか
③2x2に分けたとき、縦軸・横軸それぞれの2つの箱のラベルは適切か
④4つの箱それぞれに適切な内容を記入することができるか
⑤タイトル、軸、ラベル、分類した内容の間で齟齬がないか
⑥全体として有用なのか
フレームワークの使い方はこうしてレベルアップする
●レベル1:フレームワークをその場で何とか作れるようになる
●レベル2:フレームワークが瞬時に浮かぶ
●レベル3:フレームワークを使いこなす
フレームワークを使いこなすトレーニング
●「フレームワーク練習シート」で実践あるのみ
●フレームワーク習得のためのA4メモ書き
さまざまなフレームワークを使いこなす
●2x3、3x3など拡張されたフレームワーク
●「位置づけ、ステップ」のフレームワーク
●「因果関係」のフレームワーク
第5章 即断即決、即実行の実践ポイント
[ポイント1]普段からできるだけ迷いを持たない
[ポイント2]普段から質問にできるかぎり即答する
[ポイント3]普段から全ての仕事を1分1秒でも速くする
[ポイント4]常にPDCAを回し、ノウハウを蓄積し続ける
[ポイント5]好循環を生み出す工夫をし続ける
[ポイント6]高いやる気を維持する努力をし続ける
[ポイント7]社長が自分の仕事をするならどうするか、考え続ける
[ポイント8]普段から即断即決、即実行を心がけ、少しでも実践する
第6章 即断即決、即実行のリスクと注意点
即断即決、即実行のリスク
●拙速により仕事の質が下がり、クレームが出る
●考えずに突っ走るメンバーが出てきて、クレームが出る
●スピードについていけないメンバーからクレームが出る
即断即決、即実行しづらいのはどんなときか
●土地勘がまったくないとき(ただし、誰かに相談して土地勘を得る)
●いま決めなくてもいいとき(ただし、自分としての結論はすぐ出す)
●利害関係者が多いとき(ただし、自分としての結論はある)
●判断ミスをした場合に挽回できそうにないとき
(これだけは慎重に。ただし、自分なりのシナリオは描いておく)
即断即決、即実行のリスクを回避するには
●普段から体系的に関連分野の情報収集を行ない、土地勘を持っておく
●即断即決、即実行すべき案件が起きたら、緊急的な情報収集を行なう
●オプション立案と評価、フレームワークでの整理の習慣をつけておく
●常にバックアッププランを考え、準備しておく
●普段から迅速に動ける少人数のチームを選抜、育成しておく
赤羽雄二(あかば・ゆうじ)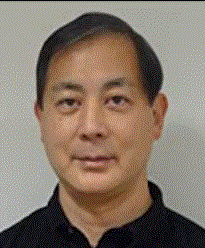
東京大学工学部を1978年に卒業後、小松製作所で建設現場用ダンプトラックの設計・開発に携わる。 1983年よりスタンフォード大学大学院に留学し、機械工学修士、修士上級課程を修了。
1986年、マッキンゼーに入社。経営戦略の立案と実行支援、新組織の設計と導入、マーケティング、新事業立ち上げなど多数のプロジェクトをリード。 1990年にはマッキンゼーソウルオフィスをゼロから立ち上げ、120名強に成長させる原動力となるとともに、韓国企業、特にLGグループの世界的な躍進を支えた。
2002年、「日本発の世界的ベンチャー」を1社でも多く生み出すことを使命としてブレークスルーパートナーズ株式会社を共同創業。 最近は、大企業の経営改革、経営人材育成、新事業創出、オープンイノベーションにも積極的に取り組んでいる。
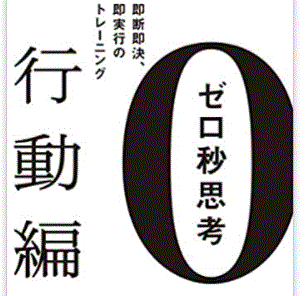
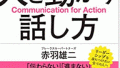

コメント