ニーチェ哲学をまとめれば無価値な世界で、自らの意志で価値を作り、それを積極的に楽しみ生きることとなる。
①非現実的な価値観を壊す(背後世界の否定)
②人生に意味なんてない(ニヒリズム)
③死ぬことすらも「死は救いだ」というありもしない意味を見出してる
④前向きに生きるには今この瞬間を力強く生きる(超人)
⑤芸術はその最たる手段になりえよう(力への意志)
哲学には、フィロソフィー(知恵を愛する)メタフィジックス(物質を超えた)という意味があり、2つに分類される。
・本質哲学:物事の本質について考える学問
・実存哲学:現実存在について考える学問
黒哲学は本質ばかり(非現実的な世界)を考える白哲学を批判するために産まれた。もっと地に足をつけた考え方を推奨していった。 白哲学に意味がある本質がある前提で物事を考えると必ずしもいいとは限らない。例えば「女性に運命の恋人がいてその人と早く出会い結婚し子供を作り温かい家庭を作って幸福に生きる。それが彼女の意味だ」でもそれは社会から与えられた意味であって、外から与えられた意味を設定して、不幸だ、絶望だと感じる。このようなありもしない意味を求めて失望する人間の構図を「背後世界」という。これにより何の目標もなくトラブルを避けてひたすら時間を潰すだけの末人になるとニーチェは提唱した。
流れとしては。
- 仕事こそ生きがい、恋愛は素晴らしいと信じられる時期がある
- しかし時間が進むにつれ退屈になりたいした意味のないことを知る
- 意味がないからすべてがむなしくなり人生の充実感や情熱を失う
- 毎日忙しく働いてひたすら暇をつぶして生きるだけの人間(末人)になる
| ●本書のPoint |
| 第一章 哲学ってなに? モノの性質や動きなど「物質的なもの」について考えるのが「科学」だとしたら(例:人間の身体など)、「哲学」とは「見たり触れたりすることができるようなモノ(物質)を越えた存在について考える学問」(例:正義・善・美・愛・幸福・意味・価値など の観念や概念)ということになる。 人間の身体でたとえると、その仕組みを調べるのが「科学」で、その身体が生きている「意味」を考えたり、新しい概念を生み出したりするのが「哲学」である。このように物事の「本質」(意味・価値)を考える哲学(例:人生の本質とは? 幸福の本質とは?など)がスタンダードな哲学で、これを「本質哲学」と呼ぶ。 一方、「実存哲学」は物事に「意味や本質はない」と考える。「実存」とは「現実存在」の略称で、意味はそのまま「(ただそこにあるだけの)現実の存在」ということを示している。日本の科学者の九鬼周造が生み出した言葉である。これまで2,000年以上もの哲学の歴史において、哲学といえば、本質や意味など、いわば「(見たり触れたりできない)非現実的な存在」をテーマに掲げる「本質哲学」のことであったが、哲学者の中に既存の哲学を批判し、これからは「現実の存在」に目を向けるべきだと主張する反骨精神を持った者たちが現れ始める。その代表的な哲学者の一人がニーチェである。 |
| 第二章 人生に意味はないってホント? 「本質哲学」では意味や本質がどこかに「ある(存在する)」という前提で物事を考える。しかし、ニーチェはそんなものは「ない」と言う。もちろん人生においても同じだ。石ころが存在しているのに何の意味も目的もないと同じで、「私」という実存(現実存在)もまた「ただそこにあるだけ」の存在であり、生きる意味や本質などというものがあらかじめ存在しているわけではない。 ニーチェはこのように「ありもしない意味を求めて失望する人間の構図」を「背後世界」という言葉を使って説明する。 ニーチェは人生の意味や本質を否定したが、ニーチェが生きた時代、特にヨーロッパでは、絶対的な価値観としてそびえ立ってきたキリスト教の影響で、人生には「意味」があると信じられていた。なぜなら、世界の創造主である神が何の意味もなく人間を作るわけはないからだ。では、そのような時代になぜニーチェは意味や本質を否定したのか。 実は、キリスト教が人々に絶対的な価値観(神・真理・本質)を与える一方で、この時代は同時に、科学の進歩による自然のしくみの解明や進化論の登場、あるいは宗教戦争や教会の腐敗などもあり、キリスト教への信仰心が失われていった時代でもあった。こうした中、ニーチェが発したのが「神は死んだ」という有名な言葉である。ニーチェは、人間に生きる意味を与えるような絶対的な価値観(目に見えない価値観)は、遅かれ早かれ、いつか壊れるということを警告したのである。 |
| 第三章 道徳なんて弱者のたわごと? ニーチェは「人生の意味」だけでなく「道徳」も否定する。「道徳」も背後世界にあるものである。たまたま、その時代、その文化でだけ通用する空想上のローカルルールである。では、なぜこの社会に「道徳」なるものが存在するのか? ニーチェは、道徳の由来を「ルサンチマン」という言葉を使って説明する。「ルサンチマン」とは「弱者が、強者に対してもつ嫉妬心や恨み」のことであるが、ニーチェに言わせれば、道徳なるものはまさにこの「ルサンチマン」から生じた歪んだ価値観であるのだ。 たとえば、モノの場合、単純に「機能として優れているもの」を「よいもの」と判断するが、人間の場合、その判断が逆になり、能力的に優れた人より「おとなしくて弱そうで質素で素朴そうな人」の方が「よい人」に見えてしまう。なぜか? ニーチェは、はるか古代の価値観では、単純に力が強い人や頭が良い人が「よい人」とされてきたが、キリスト教の登場によって「価値観の転倒」が起きたのだと説明する。 |
| 第四章 死にも未来にも意味はない? こうして「人生の意味」も「道徳」も含め、あらゆる物事における意味や本質といったものをニーチェは否定する。 だが、「人生に意味はない」「社会から押し付けられた意味づけなんか無視してしまえ」という考え方だけだと、「では、何のために生きているのか?」ということになり、「人間はニヒリズム(虚無主義)に陥って、生の高揚(=人生の充実感や情熱)を失ってしまう」とニーチェは言う。生きる意味も目的もなく、死ぬまで絶望が続くだけであれば、いっそ死んで解放された方が楽なのではないかと考えてしまいそうになるが、しかし、それでは「死」に対して「絶望や虚無感から救い出してくれる唯一の手段」という意味を見出していることになり、非実存的存在に意味や本質を認めない実存哲学の主義に反する。だからニーチェは「死」の意味すら否定する。真の絶望とは死すら救いにならないほどの絶望だ。 教会の権威が弱まっていった時代、ニーチェはまもなく「神が死んだ世界」が到来することを敏感に感じ取っていた。 |
| 第五章 それでも哲学を学べば生き方が変わる 社会の既存の価値観(常識)を根底から覆すニーチェは「絶対的で客観的な事実というものは存在しない。存在するのは解釈だけである」と言う。 ニーチェもまた、「伝統的な社会の習慣」や「奴隷道徳」など、自分自身に由来しない価値観に従って生きることを否定する。それによって自らの生を縮小させたり(萎縮してやりたいことをやらない)、自らの生を否定したり(不幸に苛まれる)することを否定した。自分自身に由来する「自然本来の欲求」によって価値を生み出して生きていこうとする「力への意志」によって生じた選択であれば、もし失敗しても不幸にはならない。 ニーチェは「芸術こそ至上である! それは生きることを可能にする偉大なものだ!」という。「芸術」とは「自分にとって価値のあると思うもの(目指してそれを表現する行為」だ。「力への意志」とは「自分にとって価値のあるものを目指したいという精神的な欲求」であるが、その「力への意志」をより具体的に現実化する行為が「芸術」なのである。また、「芸術」に結果は関係ない。「芸術」において大事なのは「自分がしたいと思うことを自分なりに追求し、その行為を心から楽しんだ(生が高揚した)」ということである。だから人生を「芸術」に昇華して楽しめばいいのだ。それが「幸福」にいたる道なのである。 |
第1章 哲学ってなに?
―ニーチェの哲学で生き方が前向きになる?(哲学ってなんですか?何の役に立つの?;哲学は「白哲学」と「黒哲学」の二種類だけ ほか)
第2章 人生に意味はないってホント?
―背後世界、ニヒリズム、末人(あなたが生きている意味ってある?;「背後世界」でわかる不幸の構図 ほか)
第3章 道徳なんて弱者のたわごと?
―ルサンチマン、奴隷道徳(ルサンチマン(嫉妬)が生み出した道徳キリスト教が世界の価値を逆転させた ほか)
第4章 死にも未来にも意味はない?
―超人、永劫回帰(人はみな「絶望」にいたる;人類最大の贈り物『ツァラトゥストラ』 ほか)
第5章 それでも哲学を学べば生き方が変わる
―大いなる正午、力への意志(ニーチェの哲学を学んだきっかけ;自分の意志の存在を疑う ほか)
著者: 飲茶
飲茶(やむちゃ)は、日本の作家。北国生まれ、東北大学大学院出。会社経営者。哲学、科学、数学などの学問をわかりやすく解説する本を書いている。


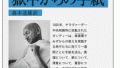
コメント