夏目漱石の晩年に執筆されたこの小説は、明治末期の東京と鎌倉を舞台に、学生の「私」と謎めいた「先生」との交流、そして先生の過去に秘められた悲劇的な恋愛と自殺の物語です。
小説は三部構成となっており、最初の部分では「先生と私」と題され、次の部分では「両親と私」と題され、最後の部分では「先生と遺書」と題されています。主人公は最初と次の部分では「私」であり、最後の部分では「先生」となります。
全3部からなるが、中心は第3部の「先生と遺書」。高校の教科書で取り上げられるのも第3部の後半部分。一般的には良心の呵責に耐えきれなくなった「先生」の自殺が主題とされるが、自制的で素直で真面目なKの自殺を「前近代的人間の終焉」とする副題も読みどころ。
【物語に登場する人物】
「私」: 最初と次の部分で語り手となる学生で、田舎から出てきました。
「先生」: 仕事をせず、妻と二人で暮らしている人物で、かつて友人のKを裏切ってお嬢さんと結婚し、罪の意識を抱えています。
「先生の妻」: 最後の部分の前半では「お嬢さん」と呼ばれており、名前は「静」です。
| ●本書のPoint |
| あらすじ 【 第1部 先生と私】 ■当時学生だった私は、鎌倉で「先生」と知り合う。先生は人を寄せ付けない雰囲気を持っていた。自分を「(交友の少ない)寂しい人間」と称し、自らの懐に入ろうとする者を、手を広げて抱きしめることが出来ないような人だった。 ■しかし、私はそんな先生に言葉に出来ない魅力を感じ、東京に帰ってからも先生の家をしばしば訪ねるようになった。 ■先生は大学卒で博識だったが仕事はしておらず、世俗の世界から逃れていた。人を信用しないその厭世的な様子は、先生の父親が亡くなった際に遺産相続で親族に裏切られたことや、学生時代に何らかの理由で親友が自害したことが関係しているようだった。 ■ある時、私は先生に「死ぬ前にたった一人でいいから、人を信用して死にたい。あなたはその一人になってくれるか。あなたは真面目か」と問われた。先生はいつか、自分の過去を私に語ることを約束した。 【第2部 両親と私】 ■私は大学卒業後、実家に戻ったが、その後の進路は決まっていなかった。父母に促されるがままに、仕事の斡旋をお願いする手紙を先生に書いたが、返事は帰ってこなかった。 ■父の容態が悪化したため、電報を打って兄を呼び寄せた。兄は先生について「人は自分の持っている才能を働かせなければいけない」と父と同じようなことを言った。父の死後も実家に戻るつもりはなく、とにかく世の中で仕事をしたいようだった。私は死にゆく父と個人主義的な兄の手前、先生に書いた手紙の返事を待ちわびていた。 ■しかし届いたのは、先生の過去を洗いざらい告白した、先生の「遺書」だった。私は父が死の間際にあるにもかかわらず、母と父に手紙だけ置いて、東京行の汽車に飛び乗った。 【第3部 先生と遺書】 ※以降の「私」は先生を指す ■私は20歳になる前に両親を亡くした。故郷の実家は資産家だったため、しきたりとして妻を娶り、家を相続する必要があった。私はそれを理解していたものの、叔父が従妹(=叔父の娘)との結婚を勧めてきた際には、さすがに幼馴染とは恋はできないと思って断った。 ■しかし後から考えると、その結婚は、事業に失敗した叔父が父の財産を総取りするための策略だった。結果的に結婚は断ったものの、家の財産は叔父に使い込まれてしまった。私は不当に減った遺産を受け取るか、叔父を訴えるかの二択に迫られたが、無駄な時間は使いたくなかったので前者を選んだ。 ■それでも普通の学生よりはお金に不自由していなかったので、下宿を出て、軍人の未亡人宅を間借りすることにした。人を信じなくなったが、愛をまだ信じていた私は、そこの一人娘であるお嬢さんに好意を寄せた。 ■私はその3人の生活に「K」という同郷の幼馴染を引き入れることになる。Kは寺の息子だが医者の家に養子に出されており、大学でも医学を学ぶはずだった。しかしKは私と同じ学科に進んだため、実家からも養家からも勘当されてしまい、精神的に参っていたのだった。 ■幼いころから成績は常にKの方が上だったが、禁欲的に自分を追い詰めるところや、女性慣れしていないところについては、私の方がよく事理を弁えていた。私がKを今の生活に引き入れたのは、未亡人宅で私自身の心身が以前より落ち着いたのと同じ効果をKに期待したためだった。 ■その後、Kは精神衰弱から徐々に回復し、お嬢さんに好意を持ち始めると、逆に私は焦り、嫉妬し、劣等感に苛まれた。しかし、学問で繋がったKとの関係性の中で、人間らしい「恋愛」の話を持ち出すのは憚られた。私はKを呼び寄せたことを後悔した。 ■ある日、Kは私にお嬢さんへの恋心を自白した。私は苦しく、恐ろしく、何も言えなかった。Kに先を越されてしまった。しかしKは完全に私を信用している。そこで私は「向上心のないものはばかだ」と、Kが以前私に言い放った言葉をそのまま返し、禁欲的な信条を持つ彼に恋を諦めさせようとした。私は卑怯であった。 ■Kに先を越されまいとした私は、先に奥さんにお嬢さんとの結婚の許可を求めた。奥さんは条件もなく快諾したので拍子抜けだった。私はKに手をついて謝りたかったが、奥さんとお嬢さんの目もあったので、それは叶わなかった。それどころか、自分からKに事情を説明することすらしなかった。 ■結局、Kは私とお嬢さんの結婚を奥さんから聞くことになったが、平静とした態度を変えなかった。それから数日後、Kは自殺した。私宛の手紙が残っていたが、私の裏切りについては書かれていなかった。正直なところ、私はほっとした。 ■私はKに策略では勝っても、人間としては負けたのだった。私は叔父に裏切られて他人に愛想を尽かしたが、Kの件で自分に愛想を尽かし、何もできなくなってしまった。そして、明治天皇の崩御、そして乃木大将がその後を追ったことを知り、自分も「明治の精神」に殉死することとした。 |
| ■学びのポイント 【近代的自由と孤独】 自由と独立と己とにみちた現代に生まれた我々は、その犠牲としてみんなこの寂しみを味わわなくてはならないでしょう。この「近代人の自由と孤独」は、本作品における最大のテーマと言われている。自由・独立・個人主義を標榜した瞬間、それらを守るために、何かに依存したり従うことは徹底的に排除される。すると結果的に、人間は周囲との繋がりを絶たれ、孤独になる。すると人は逆説的に、何かに従いたくなるということを言っている。 【父と先生の対比】 「父」と「先生」の対比も、本書を貫く主要なテーマの一つとなっている。どちらも社会に何の貢献もしていないし、存在してもしなくても、社会に影響はない。しかし、「父」は東京の大学に通う「私」から見ると、凡庸の代表である。田舎者、教養に欠ける、大学を出れば高給が得られると思っている、周り近所から見える体裁を気にするなどなど。父とは関係が近すぎて、私は父の全てを知っているものと思い込んでいる。 一方の「先生」はミステリアスである。多くを語らない、教養は深そう、何やら暗い過去を抱えている。二十歳前後の若者には、父親よりも優れている人が外にたくさんいることに気が付く瞬間がある。これは、誰しも経験することだろう。しかし「私」はそこまでドライな人間ではない。父がやたらと大学卒業を「結構なこと」を言うのに対し、当初「私」は「そこまで大したことではない」と反発する。しかし「父」が自分の死期の近いことを悟ったうえで、自分が生きている間に息子が大学を卒業するのが(父にとって)結構なことと言っていることに気付く。その卒業が父の心にどのくらい響くかも考えずにいた私はまったく愚か者であった。私は鞄の中から卒業証書を取り出して、それを大事そうに父と母に見せた。 【精神的に向上心のないものはばかだ】 (K→私) たしかそのあくる晩のことだと思いますが、二人は宿へ着いて飯を食って、もう寝ようという少しまえになってから、急にむずかしい問題を論じ合いだしました。Kはきのう自分のほうから話しかけた日蓮の事について、私が取り合わなかったのを、快よく思っていなかったのです。精神的に向上心がないものはばかだと言って、なんだか私をさも軽薄もののようにやり込めるのです。 (私→K) 私はまず『精神的に向上心のないものはばかだ』と言い放ちました。これは二人で房州を旅行しているさい、Kが私に向かって使った言葉です。私は彼の使ったとおりを、彼と同じような口調で、再び彼に投げ返したのです。しかしけっして復讐ではありません。私は復讐以上に残酷な意味をもっていたということを自白します。私はその一言でKの前に横たわる恋の行手をふさごうとしたのです。 本作品で、最も有名な一節は何かと問われれば、恐らくこの「精神的に向上心のないものはばかだ」というセリフが挙がるだろう。これはもともと、しっかりと議論と向き合わない「私」を見下して「K」が言い放った言葉だった。Kは寺の息子らしく、禁欲的で、生真面目で、強情で、誇り高い。向上心を持たない者を完全に見下していた。 しかし、そのKがあろうことかお嬢さんへの恋にうつつを抜かしてしまう。私は何とかしてその恋を止めなくてはいけない。そこで最も効果的であると私が選んだのが「精神的に向上心のないものはばかだ」と言い返すことだった。Kが最も大切にしている価値観を否定し、Kの存在自体を否定してしまう、悪魔のような仕打ちだったと言えるだろう。 |
夏目漱石 (なつめ そうせき) 1867-1916
日本の英文学者・小説家。本名は夏目金之助。近代日本文学における文豪の一人。1984年から2007年まで発行されていた千円札の肖像でもあった。1893年東京帝国大学英文科を卒業後、1895年松山中学教諭、1897年旧制第五高等学校(熊本)教授を経て、1900年にイギリスに留学。帰国後、東京帝大等で英文学を講義。1905年に「吾輩は猫である」により作家としてデビューした。その後、創作活動に専念するため、1907年に朝日新聞に入社する。代表作に「坊っちゃん」「草枕」「虞美人草」「三四郎」「それから」「門」「明暗」そして本書「こゝろ」などがある。1916年、50歳で亡くなる。高名な人物ではあるが、人生自体は不遇が多く、作品では「孤独」や「生きにくさ」といった感情が扱われることが多い。若い頃に患った肺結核、英国留学時の神経衰弱、東京帝大での教師としての不評(小泉八雲の後任だった)、そしてその後の胃潰瘍等を経て、本作品は夏目の晩年に書かれている。

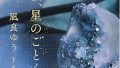
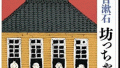
コメント